遺言書が必要な主な12ケース
遺言書は誰でも、作成しておくのがベストといえます。
ただ、以下の12のケースにどれが一つでも該当するなら、特に遺言書作成の必要性が高いといえます。
- 夫婦間に子供がいない
- 相続争いが見込まれる
- 誰に「どの財産を遺すのか」を明確にしたい
- 主な遺産が家などの不動産である
- ある相続人には遺産を残したくない
- 長男の嫁など、相続人以外の人に遺産を残したい
- 先妻の子供と後妻がいるなど、相続関係が複雑
- 内縁の妻、もしくは夫がいる
- 相続手続きを簡素化したい
- 事業承継を円滑にしたい
- ペットの世話をしてもらいたい
- 寄付したい
それぞれ見ていきましょう。
夫婦間に子供がいない
私たち夫婦には、子供がいません。
その場合でも、遺言書は作成しておいた方がいいのでしょうか?
遺言書がなくても、私の財産は全て妻が相続することになると思うのですが・・
あなたに兄弟姉妹はいませんでしょうか?
兄が一人と妹が一人おります。
そうですか。
そうなると、遺言書は絶対に作成しておくべきといえます。
子供がいない、両親も既に他界している。
このような場合、相続人になるのは、妻(もしくは夫)だけと思っている方が、少なからずいらっしゃいます。
ただ、子供がいなくて、両親(正確には直系尊属全員)も既に他界している場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
さらに、兄弟姉妹には一代に限って代襲相続が認められますので、兄弟姉妹の中で、既に亡くなられている方がいる場合には、甥や姪が相続人となってきます。
そして、兄弟姉妹が法定相続人になった場合、配偶者と兄弟姉妹の法定相続分は、以下のようになります。
- 妻(もしくは夫)・・3/4
- 兄弟姉妹(もしくは甥や姪)・・1/4
そして、遺言書がないと、兄弟姉妹(もしくは甥や姪)と遺産分割協議をしなくてはなりません。
しかし、「妻〇〇に全財産を相続させる」という遺言書があれば、話は大きく違ってきます。
まず、遺言書の内容どおりに、妻に全財産を相続させることができます。
また、兄弟姉妹(もしくは甥や姪)と遺産分割協議をする必要もありません。
そして、兄弟姉妹(もしくは甥や姪)に、1円たとりとも遺産を相続させなくても、法律的には何の問題もありません。
兄弟姉妹(もしくは甥や姪)には、遺留分がないからです。
遺言書があるかないかで、このように変わってきます。
夫婦間に子供がおらず、配偶者へ全財産を遺したい場合には、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書を作成しましょう。
相続争いが見込まれる

相続人同士が不仲である。
相続が発生した際に、あきらかに揉めることが想定される。
このような場合には、遺言書をしっかりと遺しておきましょう。
遺言書がなければ、その不仲の相続人同士で遺産分割協議をして、遺産の取り分を決めることになります。
最終的に裁判で決着をつける、ということにもなりかねません。
相続争いが見込まれる場合には、必ず遺言書を作成しましょう。
また、なぜそのような遺言の内容にしたのかや、相続人に対する感謝の気持ちを、付言事項として遺言書に記載しましょう。
相続人が100%納得するとは限りませんが、相続人の考えや気持ちを知っているのと、知らないのでは、大きな違いがあります。
遺言書で、相続人同士のトラブルを防げる可能性が高くなります。
誰に「どの財産を遺すのか」を明確にしたい
この土地Aは長男に。
この土地Bは長女に。
この土地Cは次女に。
〇〇株式は長男に。
上記のように、遺言書で「各相続人ごとに財産を指定する」ことは可能です。
なお、遺言書で具体的に、誰がどの財産を遺産相続するのか指定しない場合、相続人間で遺産分割協議をして、決めることになります。
このような場合、被相続人(亡くなった方)の想いとは、全く違った形での遺産相続となる可能性もあります。
あるいは、遺産の換価分割(遺産を売却した上で、その売却額を相続人間で分け合う遺産の分割方法)をして、後世に残し続けたいものが無くなる可能性もあります。
遺言書で指定したからといって、100%そのようになるとは限りません。
ただ、誰にどの財産を遺すのかを決めている場合には、遺言書でしっかりと、指定しておくのがベストといえます。
主な遺産が家などの不動産である

遺産がほとんど不動産である。
あるいは、持ち家の一つだけである。
このような場合、遺産分割協議が難航しやくなります。
不動産は現預金などとは違い、簡単に分割することが出来ません。
また、持ち家の場合、誰がそこに住むのか?といった問題もあります。
鳥取にある持ち家を、東京住まいの相続人に遺言で指定することは、現実的と言えるでしょうか?
遺産がほとんど不動産である場合には、事前に相続人と話し合い、遺言書の内容を決めておく必要があります。
ある相続人には遺産を残したくない
家族に迷惑をかけ続けた次女には、遺産を遺したくありません。
遺言書でそのようなことは可能でしょうか?
その次女が、あなたを虐待したり、あなたの財産を著しく減少させたりした場合には、遺言書で次女の相続権を廃除できる可能性はあります。
ある相続人には遺産を残したくない、その「ある相続人」が子供や両親の場合、遺留分というものがありますので、相続人から排除することが必要です。この廃除は
- 生前に行う生前廃除
- 遺言で行う遺言廃除
の2つの方法があります。
生前に行う生前廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求して行います。
遺言で行う遺言廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に請求して行います。
ただ、実際には請求をしても、認められる(相続人として廃除できる)ケースは、ほとんどありません。
長男の嫁など、相続人以外の人に遺産を遺したい
長男の嫁は、本当によく私の面倒を見てくれています。
そんな長男の嫁に、遺産を遺してあげたいと考えています。
遺言書を書けば、相続人でない長男の嫁にも、遺産を遺せると聞きましたが、本当でしょうか?
本当です。
いくら献身的であったといえ、長男の嫁は法定相続人とはなりません。
遺言がなければ、長男の嫁に遺産がいくことは、原則ありません。
(現在では民法が改正され、相続人以外の人にも特別寄与料が認められています。よって、長男の嫁が他の相続人に特別寄与料を請求した場合には、寄与に応じたお金を受け取れる可能性はあります。参考:介護したら寄与分で必ず遺産を多く相続できるの?)
このような場合には、遺言で長男の嫁に遺産を遺しましょう。
長男には遺留分がありますから、必ずしも遺言書どおりに、長男の嫁に遺産を遺せるとは限りません。
ただ、遺言書がなければ、全く遺産を遺せません。
相続人以外の人に遺産を遺したい場合には、遺言書は必須となります。
先妻の子供と後妻がいるなど、相続関係が複雑
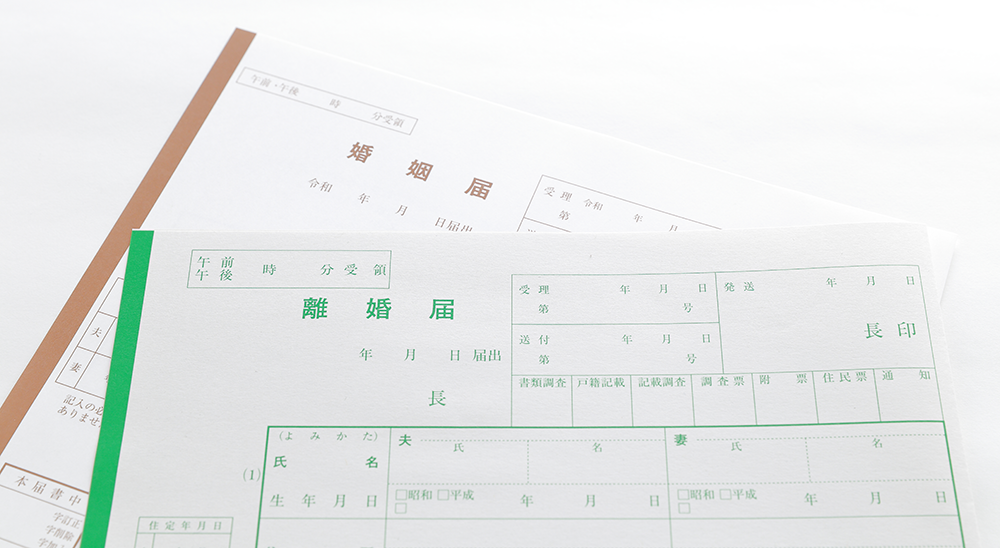
離婚をした先妻との間に、疎遠になっている子供Aがいる。
そして、再婚をした後妻Bとの間に、子供Cがいる。
このようなケースで遺言書がない場合、遺産を相続できるのは、子供A・後妻B・子供Cとなります。
たとえ疎遠になっていたとしても、子供Aにも相続権があります。
また、先妻の子供や後妻、後妻の子供がいるなど、相続関係が複雑な場合は、遺産分割協議がまとまらないこともあります。
また、子供Cに多く遺産を遺してあげたいなど、法定相続分とは異なる相続をさせたい場合もあります。
相続人間の争いを防ぎ、かつ被相続人の想いを反映させるためにも、遺言書で「相続分や遺産分割方法」をしっかりと明記しましょう。
内縁の妻、もしくは夫がいる
内縁の妻(もしくは夫)というのは、普通の男女の結婚生活と同じように、共同生活を営んでいるが、何らかの事情により、法律上の手続きをしていないため、法律上は妻(もしくは夫)になっていない方をいいます。
そして、内縁の妻(もしくは夫)は、相続人になりません。
内縁の妻(もしくは夫)に、遺産を遺したい場合には、遺言書は必須となります。
相続手続きを簡素化したい
子供たちとも既に話し合い、遺産分割の内容が既に決まっている場合、遺言書は必要ない、と思われるかもしれません。
ただ、遺言書があると、遺産分割協議をせずに、名義変更などの相続手続をすることができます。
相続人が海外などに赴任しており、バラバラになっている場合、遺産分割協議をすること自体が難しい、ということもあります。
相続手続きのことも考えると、やはり遺言書はあった方がいいといえます。
事業承継を円滑にしたい

事業を営んでいる。あるいは、農業を営んでいる。
そして、出来れば後継者に、遺産を多く遺してやりたい。
もしくは、事業や農業の経営を考えると、後継者に遺産を多く遺す必要がある。
このような場合には、遺留分に配慮しながらも、後継者に遺産を多く遺すようにしましょう。
ちなみに現在では、事業承継税制を活用すれば、相続税や贈与税なしで、後継者に自社株を承継することもできます。
ペットの世話をしてもらいたい

自分の死後、誰がペットの世話を見るのか・・
ペットは家族も同然。そういう方も少なくありません。
あるいは、自分の死後の一番の心配ごとは、ペットの世話という方もいらっしゃるかもしれません。
このような場合には、ペットの世話を見ることを条件に、遺産を相続させるという遺言書を作成しましょう。
寄付したい
私は独身で、父や母はすでに他界しています。
また、兄弟もいませんので、相続人になる方がいません。
どうせなら、私の死後は、私のお世話になった施設などに寄付したいと考えております。
遺言でそのようなことは可能でしょうか?
可能です。
相続人が全くいない場合、遺言書がないと、遺産は全て、国庫に帰属してしまいます。
自分が世話になった人や、世話になった団体等に寄付をしたい場合には、遺言書の作成が必要となります。







