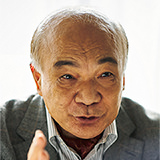遺言の作成方法は大きく分けると2つ
そろそろ遺言書を作成したいのだが、どうすればいいのやら・・
遺言書の作成方法には、大きく分けて「自分で作成する方法」と「公証人と一緒に作成する方法」があります。
自分で作成する遺言書を「自筆証書遺言」、公証役場で作成(公証人と一緒に作成)する遺言書を「公正証書遺言」といいます。
自分で作る自筆証書遺言の作成方法やメリット等
自筆証書遺言は「遺言の内容の全文・日付」を遺言者が自分で書きます。

また、署名と押印をする必要もあります。
自筆証書遺言には、以下のようなメリットがあります。
- 費用がほとんどかからない
- いつでもどこでも簡単に作成できる
- 誰にも内容を知られず、秘密で作成できる
- 自筆ということもあり、相続人の心情に説得力が増す
そして、以下のようなデメリットがあります。
- 検認が必要
- 第三者に変造・偽造される可能性がある
- 遺言の紛失や、生前に発見される場合がある
- 法的要件を満たさず、無効になる可能性がある
自分が書いて保管するので、いつでも、どこでも作成できて秘密が守られます。
証人(公正証書遺言には必要)も必要なく、費用をほとんどかけずに作成できるという長所もあります。
【遺言書=自筆証書遺言】というイメージを持たれている方は多いと思います。
しかし、遺言の内容を全て手書きで行うは、大変な労力を必要とします。
(財産目録はパソコン・ワープロでの作成が可能)
ちょっと待ってください!
そもそも、字がまともに書けない人は、どうなるのでしょうか?
うちの親父は、まともに字を書ける状態ではないのですか?
その場合は、「自筆証書という形での遺言書」の作成は出来ないことになります。
字が書けない人は、自筆証書遺言を作成することはできません。
また、代筆やパソコン・ワープロで作成したものは、自筆証書遺言とは認められません。
パソコン・ワープロでの作成も認めてしまうと、第三者がなりすまして、遺言書を作成できてしまうからです。
そして、誤記があって加除・訂正する場合も、決まった方式で行う必要があります。
決まった方式で訂正していないと、その自筆証書遺言そのものが無効になります。
また、遺言書に【具体的な日付が自筆】されていない場合も無効になります。
例えば「12月吉日」というような日付は無効となります。
このように自筆証書遺言は「方式の不備や、内容が不明」ということで、「無効になりやすい」というデメリットがあります。
遺言書に預貯金のことは書かれていないのですが、自宅についてはしっかりと記載があります。
また、方式などには不備がありません。
この場合、この遺言書は無効となるのでしょうか?
いや、無効とはなりません。
遺言書に記載のない預貯金については、相続人の話し合い(いわゆる遺産分割協議)で、どのように相続するのかを決める必要があります。
また、自筆証書遺言自体には何の問題がなくても、そもそも被相続人の死亡後に「発見されない」というリスクもあります。
遺言書は発見できませんでしたが、エンディングノートを発見することができました。
これは遺言書の代わりになりますでしょうか?
エンディングノートは遺言書の代わりになりません。
そして、自筆証書遺言書には「紛失・偽造・隠匿」などの危険もあります。
自筆証書遺言の作成は避けるべき
もしも相続人の誰かが、自筆証書遺言を発見し、その内容を見てしまった。
そして、自分に不利な内容が書かれていた。
その相続人が遺言書を絶対に「破棄・隠匿」しないといえるでしょうか?
遺言書が発見されない限り、その遺言書はなかったことになります。
また、自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
ちなみに、自筆証書遺言の封印のあるなしにかかわらず、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認手続きには、
- 申立書類
- 遺言者の関係書類
- 相続人の関係書類
などの書類を用意する必要があります。
これはかなり手間のかかる作業であるため、検認手続きは専門家にお願いすることがほとんです。
また、封印のある遺言書の場合には、すべての相続人(もしくは代理人)が家庭裁判所で立ち会い、開封する必要があります。もしも、
- 相続人が多数いる
- 行方不明者がいる
- 海外に在住している者がいる
- 成年後見人を必要とする方がいる
といった場合には、検認手続きが大変な作業となってきます。
また、上記には該当しないとしても、通常「検認の実施」には1か月程はかかります。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡後から10か月以内です。
この10か月うち、場合によっては、数か月を「遺言書の検認」にとられることになります。
このように自筆証書遺言には、デメリットが多いといえます。
遺言書の作成は、以下に記載している、公正証書遺言での作成をお勧めいたします。
公証人と一緒に作成する公正証書遺言の作成方法やメリット等
公正証書遺言は、公証人が作成します。
そして、遺言者と証人が公証人の面前で署名します。
自筆証書遺言との大きな違いは、自書が要求されておらず、ワープロやパソコン等の印字による遺言も有効となります。
公正証書遺言の作成方法の流れは、以下のようになります。
- 遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で述べる
- これを公証人が筆記する
- 筆記したものを、遺言者と2人以上の証人に読み聞かせる(または閲覧させる)
- 遺言者と証人が筆記が正確であることを認めて署名・押印する
- 公証人が方式に従って作成したことを付記して署名・押印する
この公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。
- 検認手続が不要
- 遺言を検索することができる
- 原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造等の心配がない
- 専門家である公証人が作成するので、遺言が無効になる可能性がほぼない
そして、デメリットは以下のようになります。
- 費用や手間がかかる
- 証人を通じて遺言の内容が第三者に知られる恐れがある
このように公正証書遺言にも、メリット・デメリットはあります。
ちなみに、「遺言を検索できる」というのは、公正証書遺言は、コンピュータによる非公開の遺言検索システムに登録されます。
これにより、遺言者が死亡した後に、相続人が必要書類(戸籍謄本、除籍謄本など)を用意すれば、全国どこの公証役場でも、遺言の有無を照会できるというものです。
また、ほとんど利用されることはないのですが、秘密証書遺言というものもあります。
秘密証書遺言は、遺言者が遺言を作成して封入したものを、公証人の面前に提出して、証人2名以上とともに公証人の面前で署名します。
そして、秘密証書遺言の場合には、自筆である必要はありません。
ワープロ書きや、他人に筆記させたものでも有効です。
これは公証人および証人の面前で申述することにより、遺言者の意思を確認できるため、「自筆でなくてもいい」ということです。
口頭や録音、ビデオという形で遺言の作成はできる?
現時点においては、「紙に書く」以外は遺言と認められません。
口頭を録音したものや、ビデオ撮影したものは、遺言と認められません。

また、文書を電子化したものも、遺言と認められません。
遺言書自体は自筆で書いたとしても、それをPDFファイルなどに電子化した場合には、その電子化したファイルは遺言と認められない、ということです。
本人(遺言者)が登場して、遺言の内容を述べているビデオなどは、認められてもよさそうですが、なぜダメなのですか?
確かに認めてもよさそうに思えますが、電磁的記録は、相続人が故意に編集したりすることも有り得るので、認められていません。
また、そもそも遺言作成の要件の1つである「本人の署名押印」が、ビデオや録音などの電磁的記録には出来ません。
ビデオや録音による遺言が絶対に無駄とは言えない
自筆証書遺言の場合、遺言の内容が遺言者の真意なのか?と争われるケースがあります。例えば、
- 第三者に脅迫されて書いたのではないか?
- 相続人の誰かに騙されて書いたのではないか?
といった論点が生まれやすい、と言えます。
この時、たとえ法的な効力がなくても、遺言者本人が遺言の内容を語っているビデオや録音があれば、遺言者の真意に基づくものであることを立証する手段としては有効です。
また、法的に有効な遺言がない状態でも、遺言者本人の意思はわかることになります。
相続トラブルを予防する一定の効果はあるといえます。
ただし、一番いいのは、やはり公正証書遺言を作成することです。
そして、遺言の内容については、相続税対策なども考慮して、事前に税理士と相談するのがベストといえます。
遺言は何回でも、いつでも書き直すことができます。
財産状況の変化や、相続人の生活環境の変化に対応して、毎年、遺言の内容を見直す、ということも必要といえます。
相続税対策を加味した遺言書作成なら、都心綜合会計事務所にお任せください。