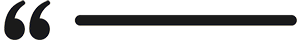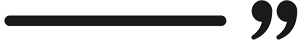公正証書遺言の費用は遺産の額で変わる

公正証書遺言を作成する際にかかる費用には、以下のものがあります。
- 公証人の手数料
- 公証人の出張費用や交通費(公証役場以外で作成する場合)
- 証人2名への謝礼
- 専門家への手数料(税理士などへ依頼した場合)
公証人の手数料については、遺産の額をもとに法律で金額が決められています。
公証役場で作成する場合の公証人の手数料
公証人の手数料は、相続人あるいは受遺者ごとに費用を算出し、それらを合算した金額となります。
そして、その費用は、相続人あるいは受遺者が遺産相続する資産の額で、以下の公証人手数料令第9条別表をもとにして決まります。
1. まず、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が、下記のとおり、定められています。
公証人手数料令第9条別表
目的の価額 手数料 100万円以下 5,000円 100万円を超え200万円以下 7,000円 200万円を超え500万円以下 11,000円 500万円を超え1,000万円以下 17,000円 1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円 3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円 5,000万円を超え1億円以下 43,000円 1億円を超え3億円以下 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 3億円を超え10億円以下 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 10億円を超える場合 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 2. 上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
➀ 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
➁ 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。
➂ さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
➃ 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
引用元
日本公証人連合会
同じ遺産総額でも遺産の分け方で手数料が変わる
遺産総額が5千万円で、妻に3千万円、長男に1千万円、長女に1千万円を遺産相続する場合の公証人の手数料は、以下の1~4の合計で68,000円となります。(厳密には、正本と謄本の交付に、1枚につき250円などの手数料がかかります。)
- 23,000円(妻の分)
- 17,000円(長男の分)
- 17,000円(長女の分)
- 11,000円(遺言加算金、遺産総額が1億円以下によるもの)
遺産総額が同じ5千万円で、妻に4千万円、長男に5百万円、長女に5百万円を遺産相続する場合の公証人の手数料は、以下の1~4の合計で、62,000円となります。
- 29,000円(妻の分)
- 11,000円(長男の分)
- 11,000円(長女の分)
- 11,000円(遺言加算金、遺産総額が1億円以下によるもの)
このように同じ遺産総額でも、遺産の分け方で手数料が変わります。
目的の価額が算定不能のものがある場合
遺言に記載しても、その金額が算定不能のものがあります。例えば、
- 長男を祭祀の主宰者とする
- 長女を推定相続人から廃除する
- 遺留分を侵害されている相続人に遺留分の放棄を促す
といったものは、目的の価額が算定不能のものとして、これら一つの意思表示ごとに1万1,000円の手数料がかかります。
公証役場以外で作成する場合の公証人の手数料
公証役場に行くことが出来ません。
その場合の手数料はどうなるのでしょうか?
ざっくり言いますと、公証役場で作成する場合の1.5倍の費用がかかります。
公証役場以外で作成する場合には、公証人の費用は、以下1~3の合計となります。
- 公証役場で作成する場合の手数料(算定不能の意思表示の金額を含む) × 1.5倍
- 公証人の日当(2万円、4時間以内であれば1万円)
- 公証人の出張交通費(実費)
注意点としては、遺産総額が1億円以下による遺言加算金11,000円は1.5倍せず、1.5倍された後の手数料に11,000円を追加します。
算定不能の意思表示の金額は、通常の手数料と同様に1.5倍となります。
証人2名への謝礼
友人が証人になってくれるのですが、この場合、いくらお支払いするべきなのでしょうか?
数千円から1万円位の料金が妥当と言えます。
証人になってくれる方への報酬は、法律で何も決まっていません。
よって、証人によっては、無償でやってくれる方もいらっしゃるかもしれません。
ただし、証人の方の時間を奪うことにもなりますので、証人1人につき数千円から1万円位の謝礼を支払う、というのが通常です。
専門家への手数料
公正証書遺言の作成相談や作成依頼を、税理士などの専門家にする場合は、その分の手数料もかかります。
なお、税理士法人・都心綜合会計事務所の公正証書遺言の作成料金は、99,800円となります。
また、遺言執行者としての報酬や、相続税の申告手数料などにつきましては、「遺言・相続に関する料金表」に記載しています。