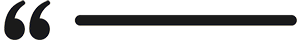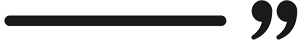パソコンで書けるが証人2人と公証役場に行く必要あり
私が生きている間には、遺言書の内容を誰にも知られたくありません。
ただ、私の死後には必ず遺言書を子供達に見てもらいたいです。
どうすればいいでしょうか?
そうですね。
そうなると、証人や公証人に内容がバレてしまう、公正証書遺言での作成が出来ませんので、自筆証書遺言か秘密証書遺言での作成となります。
秘密証書遺言?
聞いたことありませんが、名前からして良さそうですね。
どういったものですか?
簡単にいいますと、内容を誰にもバラさずに「遺言書の存在だけ」を、公証人に証明してもらう遺言書となります。
それはいいですね。
その秘密証書遺言の書き方や作り方を詳しく教えて下さい。
分かりました。
秘密証書遺言の要件

秘密証書遺言の要件を満たすには、民法970条1項に掲げられている方式に従う必要があります。
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3.遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
引用元
民法970条1項
秘密証書遺言の出来上がりまでの流れ
秘密証書遺言の出来上がりまでの流れを、簡潔に表現すると以下のようになります。
- 遺言者が遺言書を作成して署名押印する
- 遺言書を封筒に入れて封印する
- 証人2人とともに、公証人のところへ、その遺言書を持参する
- 証人2人及び公証人の面前で、自分の遺言であると申述する
- 公証人が封筒に日付などを記載し、遺言書の存在が公に証明される
秘密証書遺言は自筆である必要はない

秘密証書遺言は、自筆証書遺言のように、自筆する必要はありません。
ワープロやパソコンで記載することも出来ますし、他人に書いてもらうことも出来ます。
ただし、署名は自筆である必要があり、押印も必要です。
また、封印は遺言に押した印鑑と同じでないといけません。
秘密証書遺言の内容は自己責任

遺言書は封書した形で、公証人に提出します。
封書しているので、公証人が遺言の内容を知ることはありません。
このように、公証人が遺言の内容について関与しません。
よって、秘密証書遺言の場合、遺言としての要件が欠けており、遺言書として無効となる危険性があります。
これは秘密証書遺言のデメリットの一つと言えます。
また、秘密遺言遺言だと、公証役場で保管してくれませんので、遺言者の責任で保管することになります。
秘密証書遺言の訂正方法は自筆証書遺言と同じ
秘密証書遺言の一部について訂正をしたい場合は、遺言者がその場所を指示して、これを変更した旨を付記し、署名のうえ、その変更した場所に押印する必要があります。
平たく言えば、自筆証書遺言の訂正方法と同じです。
ちなみに、自筆証書遺言と同様に、訂正方法を間違えている場合には、その訂正の効力は生じません。
秘密証書遺言が「自筆証書遺言に化ける」こともある

秘密証書遺言のつもりで作成したけれども、秘密証書遺言の様式を満たしていない。
ただ、自筆証書遺言の要件は満たしている。
その場合は、その遺言書は自筆証書遺言となります。
秘密証書遺言は、遺言者が自ら作成するもので、公証人はその作成には一切関与しません。
なので、ある意味、秘密証書遺言は「自筆証書遺言の一種」でもあり、実際に「秘密証書遺言の要件を満たせず自筆証書遺言に化ける」ということもあります。
秘密証書遺言のつもりで作成したが、公証役場に行く前に亡くなってしまった。
でも、遺言書をワープロなど使わず、手書きで作成しており、自筆証書遺言の要件を満たしている。
このような場合、その遺言書は「自筆証書遺言としての扱い」となります。
ちなみに、自筆証書遺言・秘密証書遺言のどちらであったとしても、家庭裁判所での検認は必要となります。