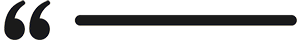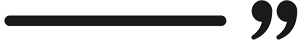自筆か公正証書遺言かで遺言を執行できるタイミングは異なる

遺言執行者に指定されているのですが、遺言者が死亡したら、直ちに遺言執行の手続きを開始しても問題ないでしょうか?
公正証書遺言であれば、遺言者の死亡後に、直ちに執行手続きに着手して問題ありません。
ただし、自筆証書遺言の場合には、すぐには着手出来ません。
自筆証書遺言の場合は検認後
自筆証書遺言では、相続人全員またはその代理人に通知し、相続人らの立ち合いのもと、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
そして、遺言執行手続に着手できるのは、家庭裁判所で検認を受けた後からとなります。
公正証書遺言の場合は相続開始後
公正証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認は必要ありません。
よって相続開始後、直ちに遺言執行手続に着手できます。
相続人の中に長年音信不通の者がいます。
それでも遺言を執行して問題ないのでしょうか?
公正証書遺言であれば問題ありませんが、自筆証書遺言の場合は、不在者財産管理人を選任した後でなければ、遺言執行をすることは出来ません。
不在者財産管理人やその選任方法については、以下のようになります。
不在者財産管理人選任
1. 概要
従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。
2. 申立人
- 利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など)
- 検察官
3. 申立先
不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
※ 不在者の財産の内容から,不在者財産管理人が不在者の財産を管理するために必要な費用(不在者財産管理人に対する報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合には,不在者財産管理人が円滑に事務を行うことができるように,申立人に相当額を予納金として納付していただくことがあります。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 不在者の戸籍附票
- 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 不在の事実を証する資料
- 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
- 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),賃貸借契約書写し,金銭消費貸借契約書写し等)
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
6. 申立書の書式及び記載例
注意点としては、公正証書遺言であれば、不在者財産管理人の選任が不要というわけではありません。
不在者財産管理人を選任し、その者に相続財産の目録を交付する、といったことは必要です。
遺言執行の期限はいつまで?
遺言執行の開始時期については分かりました。
ところで、遺言執行に期限はあるのでしょうか?
厳密に言えば、●●までに遺言執行を終えないといけない、といった決まりはありません。
ただ、現実的には相続手続きに関わる期限が、そのまま遺言執行の期限と言えます。
たとえば、公正証書遺言で遺言執行者に指定された者は「遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない」という規定があります。
そして、相続税の申告期限は、相続開始後の10カ月以内です。
相続財産の目録がないのに、相続税の申告をすることは出来ません。
また、そもそも相続財産の目録の交付がなければ、相続人はまともに遺産分割協議も出来ません。
このように相続手続きに関する期限が、そのまま遺言執行の期限と言えます。